先日、愛用していた包丁が刃こぼれをしてしまい、購入した奈良県の「三条小鍛冶宗近本店」さんへ郵送して直してもらいました。そのレポートです。
「三条小鍛冶宗近本店」とは?
奈良県の奈良公園にある刃物専門店です。歴史はかなり古く、創業は室町時代のようですが、この「三条小鍛冶宗近」の伝説は平安時代に遡ります。能の「小鍛冶」という演目が有名。以下、調べて私なりにまとめたあらすじです。
夢のお告げを受けた一条天皇の命令で、刀匠「三条宗近」は刀を打つことになった。良い刀を打つには、2人で熱い鉄を交互に打つ“相槌”を打ってくれる人が必要だが、自分と相槌が打てる有力な刀匠がいないため、一度は刀づくりを断ったが、許してもらえなかった。 困った三条宗近は稲荷明神に願をかける。すると子どもが現れて、「あなたが打つ刀は、草薙剣(天叢雲剣)などの古来の名刀と劣らぬ刀になるでしょう。刀づくりを神様が助けてくれますから、心配せず刀づくりの準備をしなさい。」という予言を残して姿を消す。 三条宗近は帰った後に支度を整え、家に祭壇を作って祈りを捧げていると、稲荷明神の眷属である狐の精霊がやってきて、相槌を務めるという。この狐の精霊に相槌を打ってもらい、三条宗近は無事、名刀「小狐丸」を打ち上げて一条天皇に献上できた。その後、狐の精霊は雲に乗って稲荷山へ姿を消した。
この「小狐丸」は現存しているのか気になり、調べました。すると…「『小狐丸』という名前の刀はあるけど、三条宗近作かは断定できない」といったところでした。一つは大阪府東大阪市の石切剣箭神社で、もう一つは奈良県天理市の石上神社。どちらかが本物なら胸熱ですが、残念ながら、失われた説も濃厚なようです…。やはり1000年も前の刀ですから、色々ありますよね。
三条宗近が手掛けた刀で現存するものとして有名なのは「三日月宗近」です。東京の国立博物館にあります。
三条小鍛冶宗近本店では、現在は刀づくりは行っておらず、包丁やハサミなどを主に作って販売していらっしゃいます。
ちなみに、今の「三条小鍛冶宗近本店」の代表の方の名前は「小鍛冶」さん。実は今回包丁の刃こぼれを直してもらうときに知ったのですが、間違いなく先祖代々鍛冶屋をやってるお名前ですよね。
もうね、ロマンを感じてしまいました…。
三条小鍛冶宗近本店で買った包丁を修理してもらうまで
購入、愛用
購入したのは2018年(だから今から4年前くらい)、正倉院展目当ての旅行で奈良公園に行ったときでした。その時に使っていた包丁は量販店で購入したステンレスのもの(以下、量販店包丁)でしたが、柄にヒビが入ってきていてそろそろ買い換えたいと思っていたところに、「三条小鍛冶宗近本店」なるいい感じの店構えの包丁専門店があったものですから、旅の思い出にもなるし、せっかくなら職人が作った良い包丁を使ってみたい、ちょうどいいと思い入店しました(だから、この時はすごい歴史があることをまだ知らなかった)。
お店の人(あれが小鍛冶さんだったのかは分かりません)が包丁のことを熱く語ってくれて、紙を包丁でスーッと切る実演もしてくれて非常に楽しく過ごさせてもらいました。包丁について知らないことが多く、大変勉強になりました。綺麗な包丁がたくさん並んでいたけれど、その中でも、普段使いしやすそうで、且つ美しい見た目が気に入った三徳文化包丁(ダマスカス V金10号 積層17層鋼 槌目 三徳包丁中寸)を購入しました。
旅行後、なんとなく勿体ない気がしてすぐには使えず、棚の中へ(^^;)程なくして量販店包丁の柄がバッキリ割れて再起不能になったのでお別れし、棚から買ってきた包丁を出して使い始めました。
生肉も、トマトも、キャベツの千切りも、ストレスなく食材が切れていくのがとっても気持ちいい!
お店の人に教えてもらった通り、カボチャとか魚の骨とか、とても固いものは切らないように気を付けました。使い始めで感動した切れ味が4年間ずっと続き、非常に満足して使っていました。
欠けさせちゃった!
今年の7月上旬。ジップロックに入れて冷凍してあった豚肉を流水解凍し、まな板の上へ。まだ氷のように冷たいものの、見た目はブヨブヨだったのでこれならサックリ切れるかと思い、包丁を入れました。
少々固い手ごたえを感じつつ、これくらいなら大丈夫と思ってグッと押し切ったのですが…
「あ…!やっちまった~~!!」

おわかりいただけるだろうか…。
解凍したと思った肉ですが、芯の方が解け切っておらず、まだ凍っていました。これが原因。
小さい欠けなんですが、大切に扱ってきただけに、絶望感が…。完全に油断した……。
このまま使い続けたら、この欠けが包丁自体や食材に悪影響を及ぼす気がします。直さなきゃ。
この包丁はやってませんが、ステンレスの安い包丁を自分で砥石で研ぐことは何回もやってきたので、欠けがなくなるまで自分で研ぎ直そうかとも思いました。でも、「自分でやって、包丁が使い物にならなくなったら?」「切れたとしても、ダマスカスの美しい模様が損なわれたら?」と考えたら踏み切れず…。買ったときにお店の人に「修理や研ぎもやるから」と聞いたのを思い出し、里帰りさせることを決断しました。
三条小鍛冶宗近本店にメールで相談→郵送→確認電話→修理開始
三条小鍛冶宗近本店のHP上に「お写真にて現在の包丁・鋏の状態を拝見させていただけると幸いです」とあったので、上の写真も添付して相談メールを送りました。次の日には返信が来て、修理可能とのことだったので、買ったときの箱に入れ、返信メールの指示通りに必要事項を書いたメモも添付し、クリックポストで郵送しました。(※買ったときの箱がなくても、刃先が飛び出さないように固定し輸送に適した梱包であれば郵送できるようです。)
数日後、三条小鍛冶宗近本店の小鍛冶さんから電話が来ました。内容は「修理後に全体が少し細くなること」の承諾を得るものでした(クレーム対策なんでしょうね。大変だ…。)。そうなるだろうと予測していたのでもちろん承諾。「何を切ったんですか?」なども聞かれました。
小鍛冶さん曰く、固いものを切るとき、専用でない安い包丁は、もっと大きく欠けたり、ひどいときにはバッキリ真っ二つに折れたりするんだそう。小さい欠けで済んだのは、この包丁が良い包丁だったからだ、とのことでした。
確かに、欠けた部分をよく見ると、割れた、というより、ちぎれた、って感じでした。つまり、「粘り強い包丁」であるということ。
前に使ってた量販店包丁は刃ではなく柄の方がダメになったから比較できないけど、確かに、量販店の安価なステンレスは良くも悪くも「固い」ですから、こうはならないんじゃないかな。

電話から10日程度で戻ってきた!確認すると…
HPには「3週間程度かかります」とありますが、私の場合、電話から10日程度で戻ってきました。代引きで3000円程度支払って荷物を受け取り、包丁を確認。


確認して一言目が「……すげぇ」
二言目が「細くなるって言ってたけど、細くなってなくない?…え??」
画像で赤い丸をつけたところが、欠けがあったところです。
修理前の写真と比べれば、確かに少ーし全体的に細くなっているのはわかりますが、比べなかったら細くなってると分かりません。職人さんが、研ぎを最小限にしてくれたのが分かります。
やはりプロに頼んでよかった。そう思いました。
前に電話が来た際に小鍛冶さんから「一生モノの包丁をお持ちだから、末永くお使いください。」と言われました。末永く使っていきたいと思います。
「あえて修理して包丁を使う」ことについて
このブログを見て、「3000円したんなら、そのお金で包丁を買い換えて使った方が良くない?」とお思いの方もいることと思います。もちろん、それも良いと思います。むしろそれが現代の道具の使い方のスタンダードでしょう。
特に、これから一人暮らしを始める自炊初心者の方や、自炊の頻度が多くない方は、量販店の安い包丁をおすすめします。私も、一人暮らしを始める際に量販店包丁を買って、それを自分でたまに研ぎながら10年くらい使い続けました。固くて錆びに強いステンレスは水につけておいても錆びる心配はないし、少々荒い使い方をしても大丈夫です。安いから悪いということはありません。
私の場合、
①物持ちが良い方で、愛着がわくと捨てられない傾向がある
②奈良旅行の記念の品である
③歴史を知ったのでロマンを感じている
④物を買うときに色々調べて比べたくなる性分なので、新しい包丁を探すのが大変である
⑤スッと切れる気持ちよさの持続、美しい包丁を所持している満足感
⑥何度も買い換えるときに発生する時間・費用のコストと、包丁自体が持つパフォーマンスを考えた時、対費用効果はトントンか、パフォーマンスが上回る
などの理由で、この包丁は捨てられませんでした。この先修理不可能なまでの損傷を起こさない限り、ずっと使い続けるでしょう。
三条小鍛冶宗近本店のほかにも、素敵な包丁を作っていて、メンテナンスも受け付けている工房は全国にたくさんあります。有名なところで私も気になっているところだと、新潟県の「庖丁工房タダフサ」とか、福井県の「龍泉刃物」とか。やはりお値段はしますが、本当に素敵ですよ!
この記事が、「一生モノの素敵な包丁を買ってみたい、でもちょっと怖い」「三条小鍛冶本店の包丁を使っているけど、メンテナンスをお願いする流れが分からない」と思う方の参考になれば幸いです。
(ただし、材質や用途によってすぐに損なってしまう包丁もあるので、勉強するか、プロに聞きながら選びましょう!)
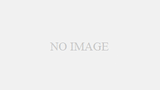
コメント