かぴです。
最近、教育界から出る話がヤバすぎて目を覆いたくなります。実はかぴは教育関係の仕事をしているので余計に感じます。
児童生徒や教員がどうとかというより、各地域の教育委員会や文科省がやることが、本当にトンチンカンすぎて…出てくる対策が大体「ソレジャナイ」感が強すぎて…。
教育界のトンチンカンとは…
結論からいうと…あくまで個人的な意見ですが、教育界には、「上になればばるほど、本質的な問題から目を背けて、トンチンカンなことをまかり通そうとしている人が多すぎる」と感じます。
どういうことか、書いていきます。
教育界の現状
最近、こんなニュースが流れました。
かいつまむと、「教員不足で、今までのような学級運営が無理になったから、学級人数の上限を見直すかも。」ということです。
昔は50人学級だったりしたので、「40人くらい」と考える人もいるかもしれません。しかしこれ、問題が山積みです。考えられることとしては…
①今、求められている「個別の対応」ができない。→家庭の多様化が進む現代のニーズを満たせない
②多くの学校の教室は40人分の机を並べるとギチギチになる設計→コロナ対策とか物理的に無理
③40人学級の担任の負担増→療休・退職者が増える
沖縄の学校事情をよく知りませんが、もっと問題はあると思います。
「教員不足なら、教員を増やせばいいじゃない」と、思いますよね。そうです。増やせばいいんです。でも、そうはならないし、増やそうとしてやっている取り組みが大体トンチンカンに見える。
少し詳しく解説します。
そもそも何で教員が不足しているの?
労働環境がザ・ブラック
かなり有名になってきたのですが、敢えてどこがブラックなのか、民間企業に例えて列挙します。
| 1、「好きで残業やってるんでしょ」という扱いで月給の4%程度以上の残業代は出ない。(8時間相当) |
| 2、でも、月80時間以上の残業をやらざるをえない職員が50%以上。 |
| 3、開店前に顧客が来る。閉店後にまだ顧客がいる。顧客がいる間は営業時間だし、カジュアルに臨時営業もする。 |
| 4、休憩は実質無し。(一応休憩時間は設けられているけど、普通に顧客対応が求められる) |
| 5、小学校の場合は8時間休憩なくずっと顧客対応。 |
| 6、昼食は自分で好きなものを食べられない、仕事の一環の「検食」込みの顧客対応。だけど費用は自腹。 |
| 7、完全週休二日制だが、中学校・高校はそのうち半日~2日間とも半強制ボランティア(部活)で潰れる。 |
| 8、5は一応手当が出るけど、3時間以上やって時給800円程度。そのへんのバイトより低い。けど責任は重い。 |
| 9、5は大会引率など必要に迫られて8時間やるハメになっても、3時間分の手当しか出ない。 |
| 10、5は拒否することもできるけど、その場合は会社の仲間や顧客からの風当たりが強くなりがち。 |
| 11、顧客から暴言、暴力、理不尽なクレームを受けても、基本的に警察にはつながらない。 |
| 12、11のようなことが起こった場合、こちらに非がなかったとしても、大体「何か対応が悪かったんだよ」と言われ謝罪を迫られる。 |
| 13、顧客のために自腹や家庭など、自己犠牲は当たり前、というか美徳とされる風潮がある。 |
| 14、以上のような状態から、鬱になる教員が毎年5000人以上出る。 |
ほかにもまだ事例がありますが、これくらいにしておきます。
離職者が増え、志願者が減っている。
病気や辞職、団塊の世代の退職で離職が進む一方で、志願者は減っています。
教員人材センターというHPで教員採用試験の倍率を眺めると…特に小学校で「1.〇倍」という数字が目立ちます。そして、これはあくまで試験合格者の倍率であり、実際はこの後採用を辞退する人もいるので、下手すると採用人数が募集数とトントンか、下回る自治体も出かねません。
教員不足への対策は?
文科省や教育委員会は、精神を病む教員が多いことや離職者が多いこと、残業についての法律(俗に特給法と呼ばれます)が1972年の実情から作られた法律であり、現代社会の現状に見合っていないことなどは既に承知しています。
1番良いのは「給料をしっかり支払い今より人員を増やす」こととよく言われます。
現状、「生徒数に対して1人の教員」などの決まりがあり、それに従って人員配置がされているので、かなりギリギリの人員で運営している状態です。だから、誰かが休むと途端にバタバタするし、1人当たりの負担も大きい。人数が増えるだけで業務にゆとりが生まれ、児童生徒へのフォローもしやすくなり、現代で必要とされる「個別の対応」もしやすくなります。
それは、もう10年も前から、現場でもよく言われてきたこと。
でも、そうはならないんですよね。
その理由の根本に「文科省が申請しても、財務省が予算を出さない」があるのだと承知はしていますが…。それでも、「いやいや文科省、教育委員会、それは効果ない、というかむしろマズくなるでしょ」という対策ばかり上がります。
実際の対策の例
| 文科省 | ①ツイッターで「#教師のバトン」創設、現役教員にやりがいや改善例を語ってもらって発信する。 |
| ②免許更新制の廃止(これはマジGJ) | |
| ③教育現場のICT化による業務効率化の推進 | |
| ④若い教員の離職原因の調査・分析(文科省の分析結果、「30~40代教員が少ないから相談相手がいないため。」ですってよ。ええぇ・・・) | |
| ⑤教員採用試験の日の前倒しを推奨(現状7,8月だが、4,5月にする、大学3年の年に受験可能にする、など。)、受験時点で教員免許がなくても2年以内に取得すればOKに。 | |
| ⑥教員免許状を四年制大学でも最短2年で取得可能にする。 | |
| ⑦部活動の地域移行の推進(2023年までに、との話だったが、この目標は撤廃された) | |
| 自治体 (例) | ①教員募集のポスターづくり |
| ②教員の魅力発信セミナー | |
| ③教員免許を持っていながら教職についていない人に向けた説明会 | |
| ④部活動の地域移行の推進 |
これらは、教育の質を保ったままで、人員確保できるような対策でしょうか。
数十年前と違い、今の大学生は情報にいくらでもアクセスでき、現役教員に容易に状況を聞くことだってできます。そこでザ・ブラックな現場の状況を聞いて「それでも教員になるんだ!」という気持ちを保てる人は、どのくらいいるでしょうか。
教員採用試験を前倒ししたって、その後の企業の採用試験に合格してしまえば、そっちに流れる人も多いでしょう。
教員免許を持っていながら教職についていない人たちの掘り出し、結構熱心な自治体も多いようですが。「それらの人々が、どうして教職についていないのか」を考えないと、結局骨折り損で終わります。
心配なのは、「教育の質を保つことができなくなるのではないか」ということです。これらの対策と採用倍率を合わせて考えると、極端な話「誰でも教員になれる!」という状態になるんです。そうすると、今まで試験で不適格とされたような人々も教員になれちゃうんですよね。
先生が子どもに与える影響ってただでさえ大きいのに。まずいことになるのではないか…と思ってしまいます。
これらの対策…一番ガッカリしていること
かぴが一番ガッカリしているのは、文科省も自治体も、現状のブラックな状態を放置したまま、ただ「魅力を発信しよう」としている対策が多いことです。これ、騙そうとしているのと同じです。
瀕死の魚が浮いている濁った池を放置して、そこを指さして「この沼、すごく泳ぎがいがあって気持ちいいんですよ!」「今なら入園料減額ですよ!」と宣伝して、来てくれる人は増えると思いますか?
池が濁る原因を除去して水質改善するだけで、魚は生き生きと泳ぎだすし、わざわざ宣伝なんてしなくても人が集まりますよね。
池が濁っている原因は、今まで何年にもわたって、何十回もやった調査で分かっているはずだろうに、改善について検討されても実行はされません。そのツケが回ってきて逼迫した状況になってきているのに、この期に及んでまだ改善しないどころか宣伝などに力を入れているところを見ると、見て見ぬフリをしている節すら感じられます。
教員自身にも原因がある
しかしこうなった原因は、教員自身にもあると考えます。
何十年に渡る長い間改善されてこなかったのは、「教員が『子どものため』と何でも請け負ってきたから」という面も指摘されています。文科省や教育委員会からのbuilt&builtな要請にも、自分の健康や家庭を犠牲にして、真面目に応えてきたし、今も大人しく応え続けているので、何も変わりません。ベテランほどそうなので、若手が異議を唱えても「教員ってそういうものだから」とねじ伏せてしまう例もよくあります。
あと、前年踏襲が多いこと。新しく何かやる、または削る、となると、同じ教員、または地域から必ず反発が起きてうまくいかない。(特に地域からの反発には弱い)
ブラック校則が話題にもなっていますが、明らかに時代にそぐわない・理不尽な校則を、なぜ守らなければならないのかの理由も説明できないのに「守れ」という教員も多いです。つまり思考停止しているのです。こういう教員が教育委員会に行ったら…どうなるか、分かりますよね。
かぴが考える、期待したい対策
先述したように、一番良いのは「人員の増員」。でも、それが叶わないなら、やることは「ブラックの原因を少しでも削ること」です。
例えば、「部活動のいち早い地域移行または廃止」「キャリアパスポートなど、現場で効果が薄いと言われる取り組みの廃止」「『総合的な学習』の見直し・廃止」「業務内と業務外の線引きの明確化」「恐喝、暴行、器物破損、業務妨害などの触法行為が疑われる事案の警察介入、弁護士介入を推進」など。
世界第三位のGDPを誇る先進国なら…
世界からみて、お金がないわけではない日本。なのに、教育に回すお金は先進国中最下位レベル。つい最近まで「30℃以上の室温でも我慢して勉強しろ」と、学校の空調に回すお金すらケチってきました。日本の教員の多忙さは世界一と言われていますが、教育にお金を使わず、教員の無料サービスや我慢に寄りかかってきたツケが、回ってこようとしています。
歴史を見ても、今の発展途上国を見ても、教育にお金をかけない国の先行きは、暗いものです。
十年以上言われてきた問題への対策を、政治も自治体も「調査します」「検討します」と先延ばしにしてきましたが、いい加減にしないと、数年以内に本当に大変なことになってしまうと思っています。

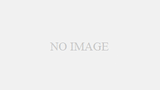
コメント