かぴです。
ちょうど1か月ほど前、こんな記事を書きました。→4/26中教審特別部会 教員給特法による給与上乗せ4%→10%以上 についての感想
中教審特別部会の提案は、まず教育現場に人を増やすための対策にはならないだろう、と思っていましたが、どうやら財務省も同じ考えのようです。→教職調整額の引き上げは「適当ではない」 財政審が建議(教育新聞)
上記の記事を私なりに要約しますと…
文科省からの教職員調整額4→10%以上に引き上げる案、財務省が「そこじゃない」と反論。
財務省的には…
①教員の仕事の負担が減るように、もっと効率的に仕事が回るように改革しなさい。
②他の行政職と比べれば、今でも給料は高い方ですよ。
③今ある予算の中で、役職抱えて頑張ってる人ほど十分な手当が出るように調整しなさい。(現状、主任とかやってても特になかったりする)
④歳出と歳入を見直して、無駄事業を洗い出して、無駄遣いをやめなさい。
財務省の言っていることを実現した方が、人手不足は解消できる気はしますね。
②は「教職調整額を含む教員に特有の手当などを合わせると、教員1人当たり平均して残業18時間に相当する手当がすでに支給されている」とありますが、18時間としても現状の実態(残業時間平均が過労死ライン大幅超過)には全く合っていないので、その現実を踏まえていただきたいところですが。
①③④をがっつりやれば、仕事の負担も、残業せざるをえない時間も減りますよね。その結果として財務省が言う「残業18時間」に短縮されれば、辻褄は合いますね。
実は前にも財務省は文科省に似たようなことを指摘していました。しかし、文科省がやったことは…
「GIGAスクール構想」→急に教育現場にタブレット配布。各種設定やトラブル対応などは教員任せ
「部活の地域移行推進」→期限を設けて地方に丸投げしたけど、できなさそうだから期限撤回
「教員の魅力PR推進」→SNSの文科省発「教師のバトン」で現場の悲鳴が世間に明るみに
「教員採用試験の期日前倒し推進」→企業より早く人材確保したいという狙いだけど…結局低倍率
「働き方改革の取組調査」→調査結果・まだ大変→早急に対応したい→実態調査 の繰り返し。現場には調査の回答に手間取らせる
「小学校のプログラミング必修化」→小学校の情報科教員はいない。現場教員が急ごしらえで対応
「小学校の高学年英語必修化」→上に同じ
などなど…。抜本的改革になっているものはなく、むしろ現場の状況を悪化させてしまっているものが多いように感じます。この数十年間で減らした学校での事業といえば、「蟯虫検査」「座高測定」くらいですし。問題なのは、特に予算をつけるでも人員を増やすでもなく新しい取り組みを現場に丸投げして、「それぞれで工夫しなさい」で済ましていることです。結果として、現場で解決策を考えて限られた人員を宛てねばならず、さらに仕事が増えている実態があります。
教育は、地域の特色が出る分野でもあるので、文科省は1から10まで「こうしなさい」と言えず、「地域ごとに工夫してやってね」と言わざるを得ないのは分かります。しかし今までそのスタンスを貫いた結果、全国的に「教員不足、教育の質低下の懸念」という共通問題が浮上してきているわけなんですよね。
文科省はもう、問題解決を各地方に委ねるのではなくて、先陣切って思い切った号令を出すべきなのではないかと思います。「新たな取り組みをしよう」ではなくて、「取り組みを減らそう」の方に。
例えば、「部活は廃止します!習い事は各家庭で!」とか、「学校の善意で出してた通知表は廃止!」とか、「2024年問題もあるし、修学旅行は廃止!」とか、「電話対応は8時~17時までです!それ以外の対応はしないし、してはいけません!」とかね。
現場が辞めようと思っても、保護者や地域から「昔はやってくれたのに」「自分は楽しかったから子どもたちにも味あわせたい」と激しい反対に遭って辞められない取り組みっていっぱいあると思うんですよ。文科省が抜本的改革の具体的な号令を出してくれれば、怒りの矛先は文科省に向かうでしょうが現場は改革を進めやすくなります。
子どもへの個別対応が求められている昨今なのに、「将来的に子ども減るから教育予算は増やさないよ」と言っている財務省に全て賛成するわけではありませんが、文科省には今一度、財務省から指摘されたことを本気になって考えて、覚悟を決めていただきたいなと思います。

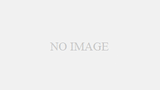
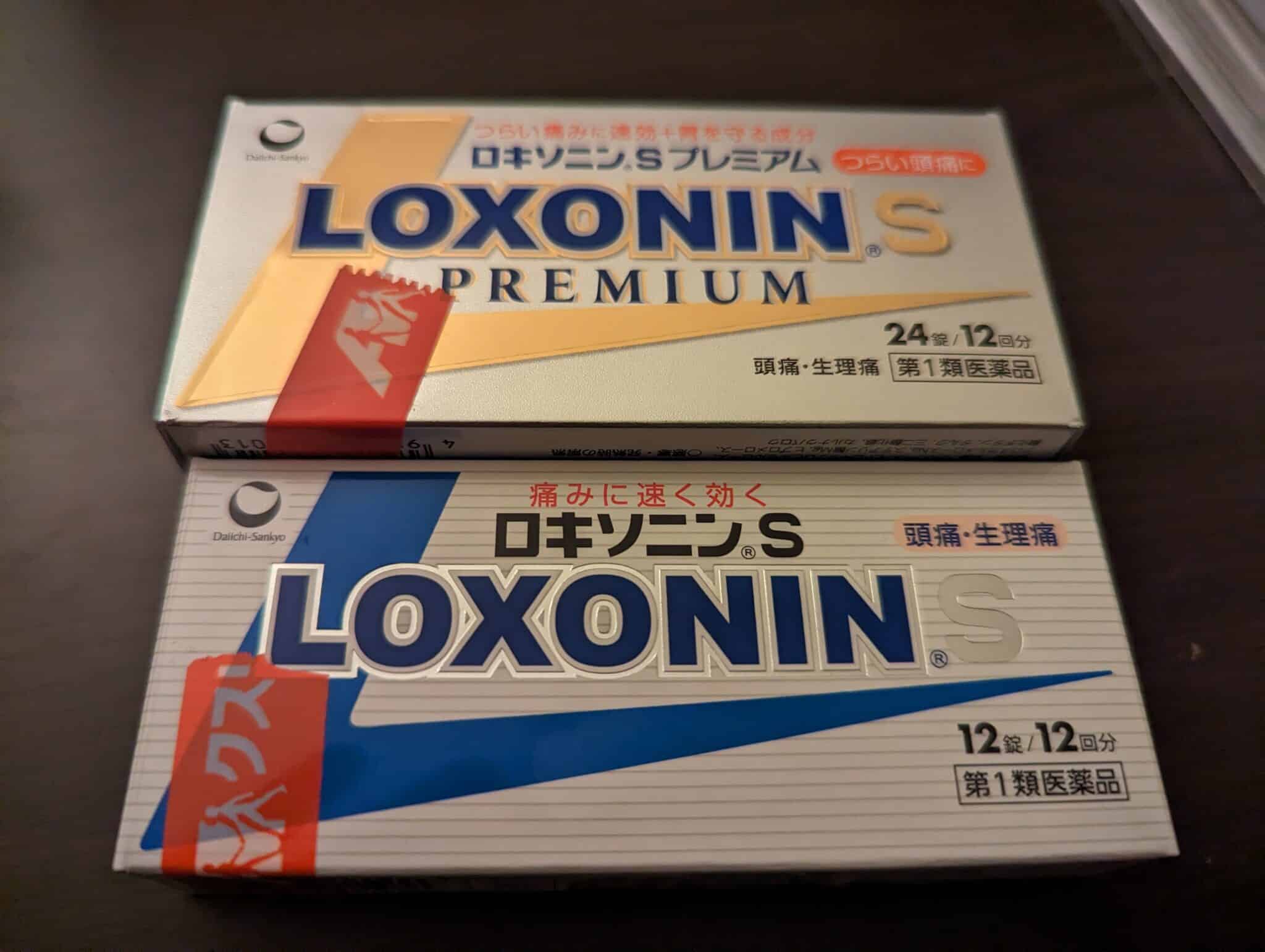
コメント