かぴです。
こういうニュースが出てますね。
教員給与 中教審部会 “一律上乗せ”の枠組み維持の意見相次ぐ
簡単に言うと…
「法律で、教員の残業を見越して月給4%上乗せしてたけど、これを10%以上になるように考えてるよ!」というものです。
メディアなどでは「教員給与上乗せ額 2.5倍以上」などと銘打たれて報道されていますが、つくづく「メディアで割合を出したら数を、数を出したら割合を気にしろ」とはよく言ったものだなぁと思います。
というのも、そもそもの「月給の4%上乗せ」というのは、月8時間程度の残業時間に相当する金額。10%だと、2.5倍、つまり月20時間相当。
でも現実は…実質的な残業時間が平均で過労死ラインを超過/日教組調査
調査によれば、教員の残業時間は平均で月100時間を超えるんですよね。はい、全然実情に合っていません。
そもそもなぜ「10%」なのかという理由について、情報番組で文科省役人の話として紹介されていたものを聞いて、耳を疑いました。なんて言ってたと思います?
「10%に根拠はない。二桁にすることに意義があった。」
おいおい…。4%ですら、「特給法制定時、月平均残業時間が8時間くらいだったから」っていう根拠がちゃんとあったんですけれど。二桁にすることに意義があったって、つまり二桁のハードルを超えられれば、段階的に上げやすいということですか?それとも考えなし??
そもそも、枠組みをなくした方が良いと思うんですけどね。「教員の仕事は裁量によるところが大きいから…」と言って枠組みをなくそうとはしませんが、世の中の仕事って、結局人間がやることですから「裁量による」ところが多いですよね。でもちゃんと残業代を出している会社も多いし、むしろ残業代を出さない会社の方が偉いところから絞られるんですけどね。その中で「教員の仕事は、やりたくてやってるところが多いから~」ってのは違和感があります。
「やりたくて」100時間もの残業をやってる人なんていないと思いますけどね。
そもそも、何でこの話が持ち上がったのかというと、教員の働き方改革の一環、そして教員のなり手不足解消という目的があったはず。
本当に、改革をしようと思っているのか、なり手不足解消をしようとしているのか、甚だ疑問です。これらが解決されないと最後に割を食うのは、子どもたちなはずなんですが…。
私の見解ですけど、「改革してるよ」感を出して問題をのらりくらりと躱して、少子化で学校が少なくなって、教員の需要が少なくなる時を待つ時間稼ぎをしているようにしか見えません。
でも、それは十年以上先の話になるでしょう。その間に公教育は崩壊してしまうのではないかなぁ。
教員のなり手不足が深刻化してきていて、それの解決のためにと、文科省や各都道府県教育委員会は「教員の魅力アピール」「ペーパーティーチャーの発掘」「教員採用試験の開催時期の前倒し」などをしていますが、私からすれば全て謎な行動です。
地獄への案内看板を設置したり特急切符をバラまいたりしても、そもそも地獄になんて行きたがる人はいません。
行先が「天国」だったら、行きたがる人も増えるのにね。
残業代云々…じゃなくて…
職員を増やして、役割の分担を進めて、残業時間をゼロにして、休憩時間もしっかりとれるようにして(現状は10分も取れていない人がほとんど)、副業などしなくても充分生きていけるだけの給与を確保する。
当たり前のことのようですが…これらが保障できてくるだけで、教員のなり手は増えると思うんですけどね。
文科省も教育委員会も、分かっているはずなのに、「頑張れ」とだけ言って、変えようと手をつけようとはしない。お金がかかるんですよね。分かる。でも、待ったなしだと思います。
「教育は未来への投資」と言われます。つまり投資しないと、未来が暗いものになってしまいます。日本の偉い人たちは、そこは分かっているのかなぁ。


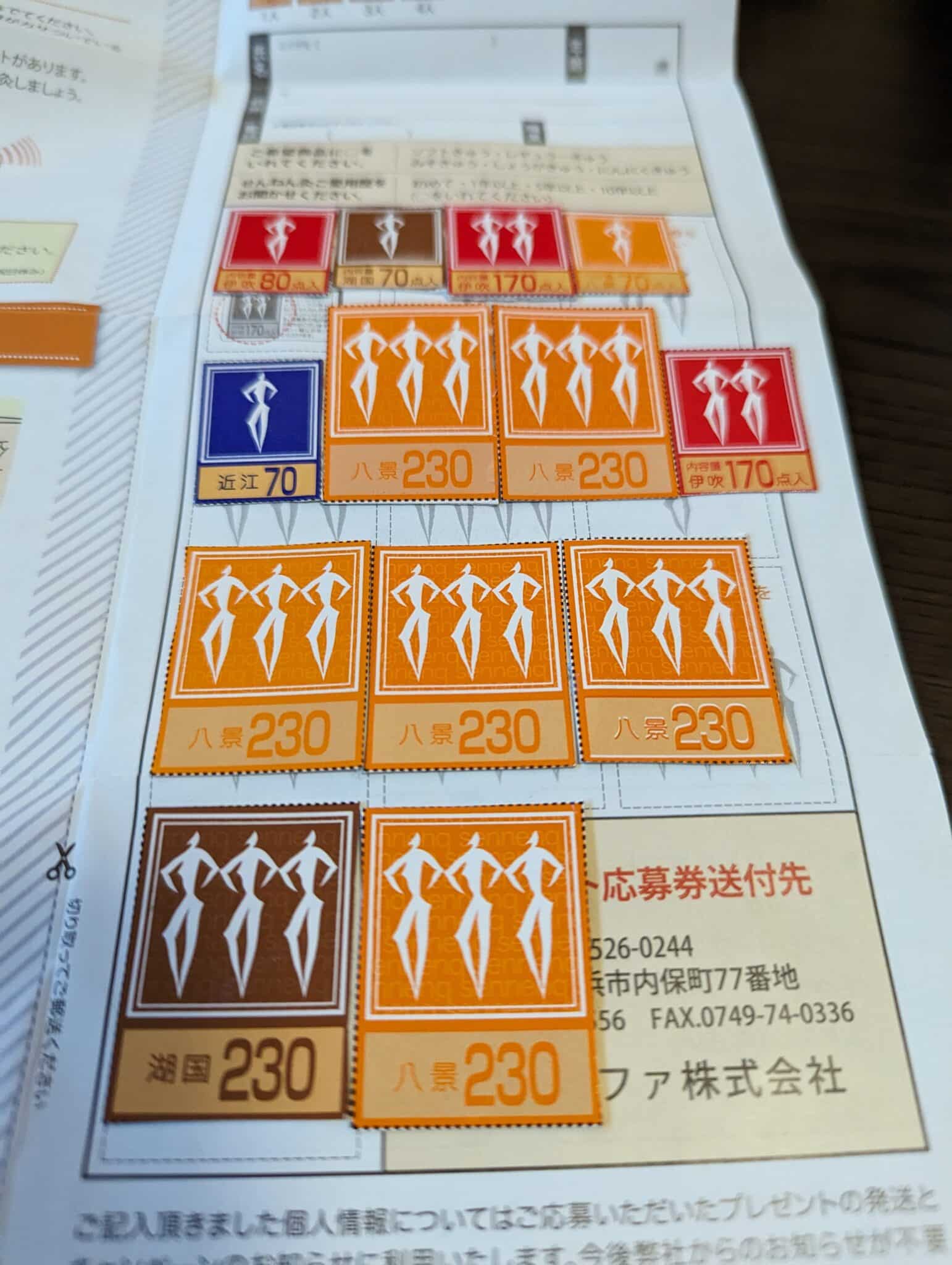
コメント