かぴです。
この記事を読みました↓
『Yahooニュース 高校不合格のゆたぼん 父らは内申点「時代遅れ」指摘に「よいことは1つもない」「否定するのはおかしい」と賛否』https://news.yahoo.co.jp/articles/40b46ea0310b2562ead18102f86d173cc7410a26
中3になって、真面目に登校して彼なりに勉強に励んでいる、というXの投稿は見たことがありました。日本一周したところまでの姿しか知らなかったので、そこと比べるとかなり背が高くなって、声も変わったな、逞しくなったなぁ、と思っていました。Xの投稿を見るに、お父さんから離れたんですね。
小学校3年生から不登校で、ホームスクーリングをやっていたということでしたが、Youtube動画投稿や日本一周をしながら、登校している子どもたちと同じだけの量(毎日6時間)の勉強をしているとは到底思えなかったので、中学3年になってそれを取り戻すのは並大抵のことではない、高校受験どうなるかな、と思っていました。
残念ながら、志望校は不合格だったのですね。
記事の書きっぷりを見て少し思うところがあったので、ちょっと書きます。
思うところがあったポイントは、次の通り。
1、『内申点』への世間の勘違い
2、『内申点』の高校受験における扱い
3、なぜ「合格は厳しい」高校に敢えてチャレンジして、その後を考えていなかったのか
4、併願は?再募集は?
5、高卒認定試験…簡単ではない
1、『内申点』への世間の勘違い
よく勘違いされるところだし、記事にあるお父さんの中村幸也さんも木下博勝さんもきっとそう思っているんだろうな、ということなんですが…。
『内申点』って、教員が恣意的に付けられるものじゃないんですよ。
内申点は何を基にしているかというと、今までの成績です。これは絶対です。で、今までの成績、つまり毎学期の通知表に記載される成績をつける際は、教員には「説明責任」が生じるのです。何か問い合わせがあったときに、必要とあればデータを引っ張り出してきて、客観的に説明できなければなりません。説明できない成績の付け方は、しちゃいけないし、問題になった場合は、その教員だけではなくて教頭や校長が頭を下げなければならない事態に発展します。
また、内申点については教員が一番神経質になるところです。通知表の成績よりもピリピリします。何しろ、ミスでも何かやらかしたらすぐニュースになりますから。全職員が点検し、それを教頭が点検し、校長が点検と、三重以上にチェックします。そうやって、今までの成績と整合性が取れているか、説明責任が取れないような数字や文言がないか、一字一句ミスがないかまでくまなくチェックするのです。もし内申点を恣意的に付けていたら、「これ明らかにおかしいじゃん!」と必ず誰かが突っ込むし、説明できなければ本来の妥当な点に訂正させられます。
もう1つ勘違いされているであろうこと…「内申は生徒の悪い行いを押さえつけるためのもの」とコメントしている人がいますが、内申にそんな力はないです。なぜなら、内申には「悪いことは書けない」のです。今までの生活態度がいかに悪かろうと、問題を起こそうと、内申には書けない。内申に書けるのは、その生徒がやってきた役割や取得資格、がんばってきた活動、部活動の成績などの、「良い実績」だけです。だから、もし教員が「内申に傷がつくぞ!」なんて言ってたら、それは虚偽の脅迫になります。
逆に、実績を何も残さなかった生徒は内申に何も書けません。それを見て高校側が何を思うかは、高校のみぞ知る…です。
このように、『内申点』について、学校側は世間が思っているほど恣意的には内申点をつけてないし、むしろ相当気を遣ってつけています。
しかしながら、現状の「内申点」の問題について、「学校ごとに差異が出てしまう」というのはその通り。と思います。成績をつける際の材料に使われる定期テストは、企業が作ったテストか、教員が手作りしたテストですから、学校ごとにテストの難易度に差が出ます。何を重視して評価するかについても、学校ごとに少し差が出ることも多いです。なので、例えばA学校ではテストの点が非常に重視されて〇△×のうち〇の実力とされていた子が、Bの学校ではA学校より提出物の点の比重が重くて△の実力にみられてしまう。みたいなことが起きます。
理想は、全国または都道府県一律で評価基準が決められていればいいんでしょうけれどね。文科省や都道府県の教育委員会が「各自治体/学校の判断にゆだねる」としているので、そうならないんですよね。私立ならまだしも公立ならば、もう少し文科省や教育委員会がリーダーシップ取ってもいいんじゃない?と思います。
2、『内申点』の高校受験における扱い
高校によるところも大きく、ゆたぼんが言う通り沖縄の公立学校は「内申点を重視している」のかもしれません。それはそうなんですけれど、全国的には、高校受験においては「内申点は、合格枠ギリギリのテスト点の人を、合格枠の人数まで振るい落とす際の材料」なんです。
例えば、合格点80点の人が2人いたとして、そのうち1人を落とさなければならないときに、学校での様子を知るために内申点を参考にする。って感じです。
だから、中学の教員が頑張って内申作ったのに、高校で一度も見られずに終わる、ということもあるあるだそうで(苦笑)
ゆたぼんは「自己採点したらテスト点は友達の倍以上あったのに、友達は受かって自分は落ちた。」と言っていました。これが真実だとすれば、彼が受けた学校はかなりの「内申重視」の学校だったのだろうなと思うし、ゆたぼんの担任は、この学校だと確実に負け戦になることが分かっていたから「合格は厳しい。」と他の学校を勧めたのだろうと思います。真実でないなら、単純に彼のテスト点不足ですね。
3、なぜ「合格は厳しい」高校に敢えてチャレンジして、その後を考えていなかったのか
先述の、ゆたぼんの担任の「合格は厳しい。」と言われたという話について、厳しい理由も聞いたはずですが、なぜ「イケる」と思ったのか。そして、なぜ「イケなかった場合」を考えていなかったのか。
「合格は厳しい」の理由として考えられるのは、「志望校が完全に内申重視だったから」か、「今までの点数では全然合格ラインに届いていないから」か。これらのどちらか、または両方だったはずです。
それを聞いても彼が挑んだのは、それほど魅力的な志望校だったからなのでしょうか。もしくは、このレベルくらいの高校には行かなければ、というプライドがあったのでしょうか。
あと、受験は、有利でも不利でも必ず「受からなかった場合はどうするか」を考えておかなければなりません。不合格になった後に再募集の高校を探したり期限を守って書類を作らねばならないなどあって考えている暇はないので、すぐに次の行動が取れるようにするためです。しかし、彼は不合格になったと結果報告したあと、「これからどうするか、また決まったらお知らせします」と動画を終わりました。不合格になった後にどうするか決めていなかった可能性が高いと思ってしまいます。
合格できる確率が非常に低いことが分かっていたはずなのに、実際に不合格になって「すごくショック」と言ったのは、つまり合格できることをかなり期待していたということだし、だから不合格になった場合のプランを考えていなかったのだろうと感じてしまって、ちょっと見通しが甘すぎないか、と思ってしまったのでした。
そしてお父さんである中村幸也さんの「合格できなかったのはゆたぼんの努力不足のせいじゃない。内申点という仕組みのせい。」とでも言いたげな言い分について。今まで「学校は行きたい子は行けばいい。行きたくない子は行かなくていい」と主張してきましたが、この度息子であるゆたぼんが高校に行きたがりました。大人である彼は、いくら自分がその仕組みが嫌いだろうと関係なく今の世の中は『内申点』というものが受験で使われるという事実があるのが分かっているんだから、息子が高校に行けるように、内申を少しでも良くできるようにサポートするとか(しかし彼はゆたぼんから離れて遠くにいたようなので、そういうサポートはしていないでしょう)、テスト点で勝負させたいなら内申点を重視しない高校を勧めるとか(そんな高校は全国見渡せばめちゃくちゃたくさんある)、文句垂れる前にできることあっただろうに。親として見通し甘すぎないか。と思います。
4、併願は?再募集は?
これは単純に疑問なんですけど、私立の併願はしていなかったのでしょうか?沖縄県は、再募集がかかった高校はゼロだったんですかね?それとも、あったけれど、志望校落ちたら高卒認定試験、って内々に決めていて、ゆたぼんが応じなかったのでしょうか?
普通は、合格が厳しい高校にチャレンジするなら滑り止めとして、私立併願したり、再募集をかけそうな高校に目星をつけておくものです。
どこの都道府県も大抵再募集をかける高校がいくつか出るイメージなんですが、沖縄はどうだったんでしょう?ちなみに、再募集でも枠が埋まらなくて、再々募集をかける高校もたまにあります。あと、通信制の高校は大抵再募集、再々募集をかけて、3月末まで応募を待ってくれています。
再募集はあったけれどゆたぼんが応じなかった、ということであれば、志望校にこだわりを持っていたんだろうな、と思います。
※4/16追記
再募集はあったみたいですね。再募集に応募すれば高確率で合格しますので、ということは、そちらは受験する気はなく、最初から「高校受験は一発だけ、それでダメなら高校行かない」と決めてた可能性が高いですね。
5、高卒認定試験…簡単ではない
さて、不合格結果が出た後、少しして彼は「高卒認定試験を受ける」という決断を下しました。
3年間自主学習を重ねて、高卒認定試験に合格すれば、高卒程度の学力があるとお墨付きがもらえて、大学進学が叶います。
学校に行かず家で学習して合格すれば高卒と認められる、と聞けば、不登校の生徒には美味しく見えてしまうこの制度ですが、実際には非常に大変です。なぜなら、特段勉強が好きでなければ、常に自分に鞭打って自分と戦い続けなければならない3年間になってしまうからです。
学校に通っていれば、多少やる気がなくても教員のサポートを受けながら毎日6時間学習するためそれなりの学力をつけることができますし、怠けたくても生活環境や教員、仲間がそれを許しません。それなりに頑張って留年せずにいられれば、3年後に自動的に高卒になれます。
しかし、学校に通わずに自宅で、となると、上記の生徒たちと同等の学力を、教員のサポートなしで自分の力だけで身につけなければなりませんし、つい怠けてしまう自分を窘めてくれる存在はほとんどいません。3年間ほど経ったら半年に1回の高卒認定試験を受けますが、その高卒認定試験の合格率は、毎年50%に届きません。2人に1人以上は不合格になっています。そこで不合格になったら高卒は遠のき、そこから半年ずつ、合格するまで頑張らなければならなくなります。
ハッキリ言って、学校に通った方がイージーモードです。
ゆたぼんは、ハードモードの道を選択しました。
4月になって、高卒認定試験の勉強のあとにボクシング練習に行く、など彼なりにリズムをつけて頑張っているようですが、その努力が3年間続けばあるいは…と思います。
色々書きました。ちょっとすっきり。
ゆたぼんが動画内で語った「結果は結果。受け入れて次に進む」という言葉は、その通りだと思います。
Youtubeで少年革命家として有名になってから「学校に行きたい子は行けばいい。行きたくない子は行かなければいい」「人生は一度きり!自由に生きよう!」と主張してきた彼ですが、「人生は勉強や!」と悟って受けた今回の受験は、本当に内申点のせいで不合格になったのであれば、「真に自由に生きるためには、やりたくないこともやらなければならない」と十分に学んだ出来事だったのではないでしょうか。彼は思春期。言葉のうわべだけを捉えた薄っぺらい主張ではなく「本当にそうなの?」と深く考えられる年齢になってきています。
高卒認定試験に合格したら、どうしようと考えているのでしょうか?大学進学??
先述した通り、自分に鞭打つハードモードの生活になると思います。今回の受験で学んだことをバネに、本当に自分の思うように「自由に生きる」ことができるように、自分に負けないでいけるといいですね。

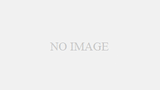
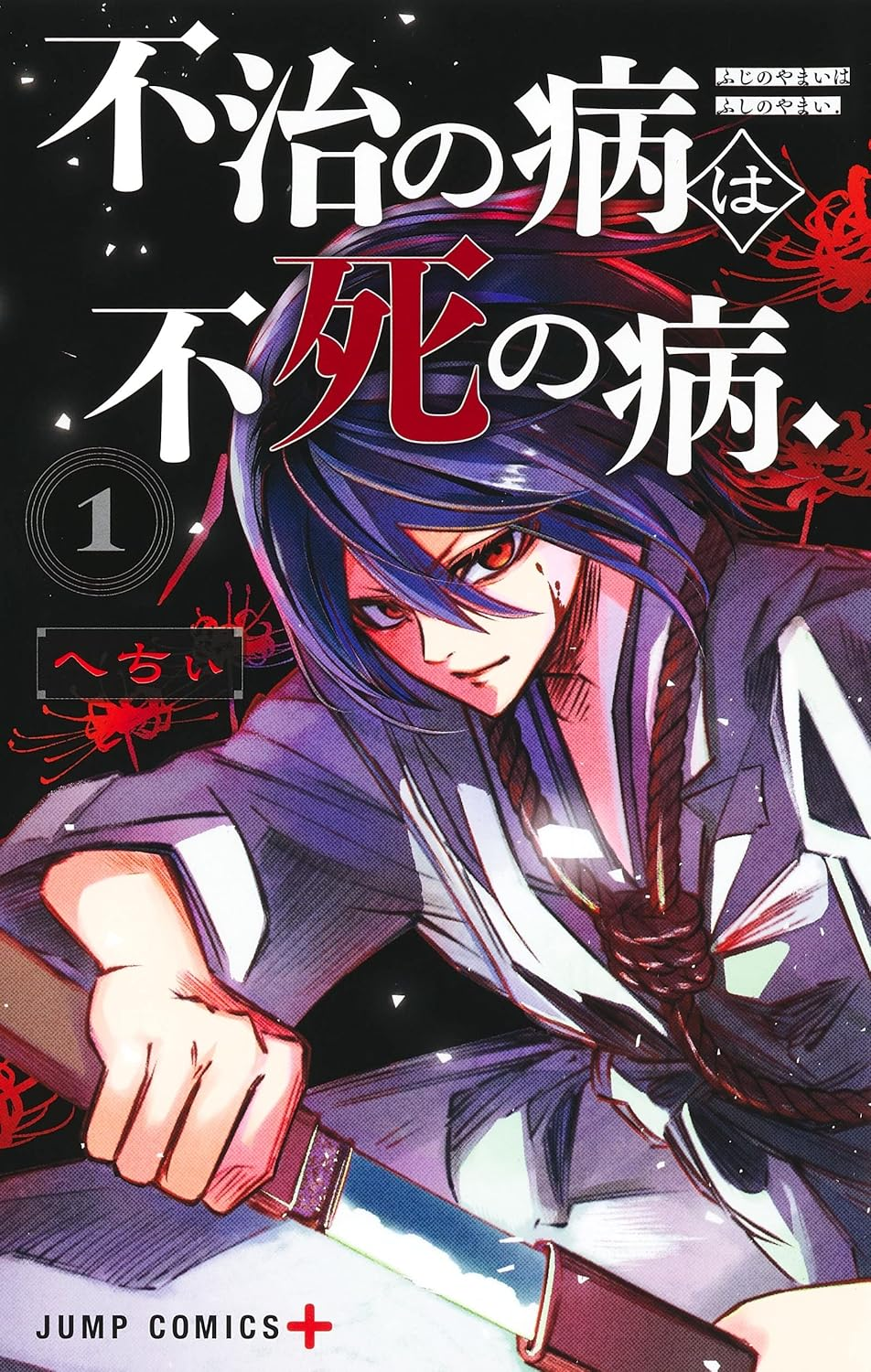
コメント