かぴです。
その1のつづきです。
「神風が吹いて、元軍壊滅」…は間違っていた?
文永の役、嵐のために撤退…ではない!説が濃厚
旧暦の10月20日、日本の記録には「朝になったら、博多湾を埋め尽くしていたはずの船も兵士もきれいさっぱりいなくなっていた」とあります。さらに、貴族の藤原兼仲という人が書いた日記には、「逆風(南風)が吹いて元の船が押し戻されていった」とあります。これにより、「神風が吹いて元軍を撃退した!」と長く日本人が信じることになるのですが、実際は少し違ったようで…。
時期的な問題
旧暦の10月20日は、現代の新暦だと「11月19日」に相当します。この時期はまず台風は来ません。
元軍の記録
11月19日あたりといえば、もう北風が吹く時期ですよね。当時の船は帆船なので動くのに風は非常に重要です。北から南に行くにはスピーディに行けるけれど、逆向きに素早く移動するためには、南風が欠かせません。そして元軍の記録によると、会議にて「日本の武士、思ったより強いから、これ以上粘ると逆にやられるかも…。」と話していたそうです。藤原兼仲の記録が正しければ、ちょうど軍が帰る方針を固めたところで貴重な南風が吹いたので、即決して身をひるがえしたと考えられます。
文永の役の撤退理由のまとめ
つまり、「嵐に遭って退散した」のではなくて、「元々帰ろうと思ってた」という説が濃厚だそうです。
しかし、高麗の記録によればちょうど帰り道の日本海近辺は暴風雨だったそうで…。玄界灘にて遭難した船が少なくなかったようです。元軍には13,000人が亡くなる被害が出ました。派遣した人数の約半数が戦いでないところで死ぬとか…兵士としても無念だったでしょう。
弘安の役、嵐も理由…だけど、メインはそれじゃない!説が濃厚
弘安の役があったのは旧暦7月1日、現代の新暦だと「8月4日」に相当します。台風や夕立などが多い時期ではあります。実際、暴風雨を元軍が襲ったという記録もあるのだそうです。
しかし、元軍が撤退した理由は、どうやらそれがメインではないようです。
元々弱かった士気が下がる一方
元軍の船は4,400隻も来ましたが、その内訳は先遣隊・東路軍900隻、主力隊・江南軍3,500隻です。そしてこの「東路軍」は、元に支配された高麗や南宋出身の兵士たちでした。なので、そもそも「元のために命を懸けよう!」という気迫は薄かったと想像できます。そして相手は、文永の役で学んでいっぱい対策を講じた、手柄を立てなければと息巻く鎌倉武士たち…。
この時の鎌倉武士の活躍は一記事書けるくらい濃いので一旦置いておきますが、とにかく、東路軍は大変な苦戦を強いられます。江南軍の到着も予定より大幅に遅れて、その間に戦死や病死でたくさんの兵士が亡くなりました。
東路軍の兵士たちは、一刻も早く帰りたい気持ちでいっぱいだったでしょう。
海上生活が長すぎた
江南軍も予定より遅れて到着しますが、元軍は既に約3か月の海上生活を送っていました。戦いが長くなると予想して、食べ物はもちろん上陸して畑を作る準備までしてきたようですが、鎌倉武士に阻まれて長く上陸することもままなりません。そのうちに食料が残り少なくなりました。文永の役で元軍の戦いから学んだ、ヤル気満々の鎌倉武士も容赦がありません。
やはり、元軍の兵士たちは、一刻も早く帰りたい気持ちでいっぱいだったでしょう。
トドメの暴風雨
海上での長い戦いに疲れ果てた元軍が退却を決めた出来事、それが「暴風雨」だったといわれています。暴風雨で、元軍は被害を受けました。
ただし、この被害は、一般的には「壊滅的」と表現されますが、歴史学者である服部秀雄教授によれば「ほんの少しだけ」だったそうです。実際、弘安の役の際に沈没した船が2011年に発見されましたが、1隻だけです。4,400隻の船が「壊滅的被害」を受けたなら、何百年も経っているとはいえ欠片でも複数発見されていても良さそうなものですが、そうではないということからも、実際に嵐で沈んだ船は少なかったのかもしれません。
弘安の役、撤退理由のまとめ
つまり、嵐はきっかけにすぎず、その前にボロボロで「もう帰りたい」となっていた説が濃厚だそうです。
鎌倉武士が彼らをいかに攻めたかを知っていると、「もう帰りたい」と思う気持ちも非常によく分かります…。いやもうホント、ゴリラみたいなので……。
まとめ
というわけで、よく言われる「神風により元軍は~」の真実は、「神風」はきっかけにすぎず、どっちも元軍が”理由のある撤退”をしたというのが最近の説だそうです。
もちろん、諸説ありです。

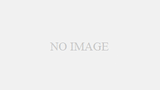

コメント