かぴです。
タイトル通り、元寇の際の鎌倉武士の蛮z…戦いっぷりをご紹介します。
元寇での鎌倉武士の戦い方 文永の役編
苦戦してなかったかもしれない。
学校の歴史の授業などでは、「鎌倉武士は個人戦法、対して元軍は集団戦法で『てつはう(火薬)』も使って攻撃してきたために苦戦した」と習います。また、当時の鎌倉武士の戦いの作法として、「『やあやあ我こそは―』と名乗りを上げて、『いざ尋常に勝負!』と戦いに挑むのが普通であった」とも言われています。
しかし最近の研究で、「これは間違いの可能性が高い」といわれているそうです。
日本軍苦戦説の出典元の「八幡愚童訓」がファンタジー要素強すぎてかなり怪しい
苦戦したことが書かれている史料が「八幡愚童訓」というものですが、この史料、かなりファンタジーなんです。例えば…
「元軍の兵士は日本軍の武士を袋叩きにし、その武士の内臓を抜き取って食べた。」
いやー、きついきつい…。元は当時、世界で一番大きな国であり、ユーラシア大陸全体の文化に影響を与えた先進国でもありました。人間の内臓を食べるなんて、そんな原始人でもやらないようなことをやったとは到底考えられません。というか、戦場においてそんな悠長なことやってられませんよね…。
「夜に、筥崎八幡宮という神社から30人余りもの白装束の集団が出てきて元軍を打ち、元軍は大混乱に陥って海まで逃げた。」
「元軍が逃げた先の海では炎が上がり、そこから2隻の軍艦が現れて元軍の船を蹴散らした。」
「残った元軍の船は大きな風が吹いて海の向こうに吹き飛ばされていった。」
…どうですか?すっごくファンタジーでしょ??
ちなみに、日本軍が個人戦法だったということはこの史料にしか書かれておらず、元の史料や鎌倉武士たちによる報告書などには、そのようなことは一切書かれていないそうです。
まぁ、ファンタジーなのは仕方ないです。「八幡」という名前がついている通り、この史料は八幡神社のありがたみを上げるために書かれたものなので…。「鎌倉武士たちが歯が立たないほど屈強な元軍を、神の力がその圧倒的な力で追い払ってくれたのだ」という話にしたいんです。
蒙古襲来絵巻
教科書での「元寇」を描いた絵としておなじみのこの絵。竹崎季長(下の絵の馬に乗ってる武士)と言う人が、自分の功績を幕府に訴えるために書かせたものです。

絵巻のため、左右に長なっています。見てみましょう。よく見えない方々はこちらをご覧ください。

…あれ?と思いませんか??
特にココとココ。


①の方は、モンゴル軍の絵のタッチと戦いに対する姿勢が明らかに違いますよね。絵巻の全体的なタッチからして、逃げている方は元々、立ち向かっている方は後から加筆されたものと推測されます。
そして、矢の方向にも注目です。ほとんど元軍側を向いてます。つまり、元軍の人たちは飛んでくる矢の雨から命からがら頑張って逃げているんです。
②は…見ての通り、普通に集団戦法やってる。
この絵巻自体が、竹崎季長さんが「俺、こんなに頑張ったんだよ!」と訴えるために作られていますので、元軍がやられている様子を誇張して描いている可能性も高いですし、この絵の中で竹崎季長さんだけ集団を離れ単騎で敵に立ち向かっていっているのも本当はフェイクかもしれません。いずれにしても、日本の鎌倉武士たちが本当に個人戦法をやっていたなら、絵巻にもその様子を描くはずですが、描かれている姿は明らかに「集団戦法」やってますよね。
「てつはう」、恐れるに足らず?
日本の武士は未だかつて見たことがなかったため、苦戦の一因となったといわれている「てつはう」。実は、実用的な武器ではなかった可能性があります。
それは、てつはうの「重さ」にあります。
「てつはう」は、陶器製の器の中に鉄の欠片や火薬を詰めた武器です。投げて破裂させて相手にケガを負わせたり、びっくりさせて混乱させる役割がある、と言われていますが…
重さは2~4㎏あったそうです。
これを人間が素手で投げたところでそんなに飛びません。相手陣営に投げ込みたいならかなり近寄らなければならないですが、非常に危険な行為なので積極的にやったとは考えられません。では道具を使ったのかと思いますが、どの史料にも「てつはうを投げる道具を使った」などは一切書いてありません。てつはうを初めて見た日本の武士が「てつはう」のことを記録に残すのに、それを飛ばすための道具をスルーするなんて、ちょっと考えられませんよね。
実用の面と記録の様子から見て、「てつはう」は本当に使われていたのか分からないのだそうです…。
急襲、そして追撃戦
「文永の役」は、2回あった侵攻のうち1回目のことを、当時の元号をあてはめて名付けたものです。「戦い」は複数個所で行われました。特に有名なのが「赤坂の戦い」と「鳥飼潟の戦い」で、「赤坂の戦い」は蒙古襲来絵巻に書かせた戦いですし、「鳥飼潟の戦い」は現存している鎌倉武士の報告書に書かれている戦いです。
これによれば、早良郡から上陸して赤坂の松林に軍をはった元軍を急襲したり、偶然遭った元軍と戦いを始めたりするなどして元軍を攻め立て、逃げた元軍を追撃していたそうです。
急襲する前には「赤坂は馬が使いづらい。馬の得意な場所までおびき寄せて、騎乗から一斉に射かけよう」という作戦を立てていたのに、一部の武士が早まったようですね。血気盛ん過ぎますね。武士なので当然ですが…。
元軍の記録
元軍の会議の記録によれば、「海からいなくなった」すこし前頃に、軍事会議を開いていたようです。内容は、「日本の武士、思っていたより強いからこのままだと逆にやられるかもしれない。」「食料も尽きてきたし、そろそろ帰りたい。」というものだったそうです。
もし元軍が戦局を有利に進めていたなら、会議で「思っていたより強かった」などと言うでしょうか。食料が尽きてきたのなら相手から奪えばいいのですが、それが出来なかったのはなぜでしょうか。答えは、上の通りでしょうね。
八幡愚童訓以外の史料によると、「文永の役」はこんな戦い。
博多の浜に、元軍が武装して上陸する。目的は、国交の申し出を無視した「日本への揺さぶり」。
迎え撃つは日本軍・鎌倉武士たち。
元軍は本隊を盾で守り、ドラで合図を出して進撃。剣に弓矢を主力として鎌倉武士に迫る。一方鎌倉武士たちも集団で馬に乗り、元軍に弓矢を打ちまくる。集団と集団がぶつかり合う激しい戦いとなった。
元軍が戦いに疲弊し食料危機に陥りかけた頃、南風が吹いたのに乗じて元の船は撤退していったため、勝ち負けははっきりせずに戦いが終わった。
元軍は格下と思っていた相手の手ごわい抵抗に遭って苦戦し、帰る途中で暴風雨に遭って被害が拡大するなど散々なものになったが、日本軍にとっても今回は史上初めての海外からの侵略を防ぐ防衛戦争であり、大変消耗するものとなった。
もしかしたら、こんな感じだったのかもしれません。
余談ですが、日蓮宗の祖・日蓮が書き残した伝聞によれば、壱岐島などに住んでいた民間人は元軍によりひどい被害を受けたようです。殺戮・略奪・人質、本国に連れ帰って奴隷化など。
やはり戦争、悲しい被害はありました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
小学校・中学校で習ったのとは違う「文永の役」の様子が見えてきたのではないでしょうか。「文永の役では、日本は苦戦した」のではなくて、本当は「強さで元軍をびっくりさせた」なのかもしれませんね。
ところで、日本の鎌倉武士はこの戦いで、元軍の様子をしっかり観察していたようで…。
「弘安の役」でのバーサーk…戦いっぷりはまた次回ご紹介したいと思います。

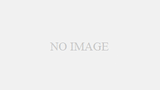

コメント